
驚異の「バランス栄養食」そら豆の魅力に迫る!
そら豆は初夏を代表する野菜の一つ。
実は食べるだけで元気が出る天然のバランス栄養食なのである。
そら豆は春の終わり頃に店頭に並び始め、夏の訪れとともに姿を消してしまう。
一年中手に入る野菜が多い中、そら豆は旬の時期にしか食べられないのだ。
そら豆は低温の環境でないと花芽がつかないため、秋にタネをまいて越冬し、春から初夏に収穫する。
ハウス栽培は採算が合わないため、露地栽培が基本。3~6月ごろにしか出回らないのである。
実はこのそら豆には小さな体にぎっちりと栄養素が詰め込まれていることをご存知だろうか。
今回は、人類最古の作物ともいわれるそら豆は天の恩恵を存分に受けた奇跡の豆「そら豆」の魅力に迫る。
ビタミンB1とB2が大量! 食べるだけで疲労回復
そら豆は太古の昔から、体力をつけたり気力を充実させるのに適した野菜といわれていた。
人類最古の作物という言い伝えもあるほどだ。
野菜の中では水分が少なく、各栄養素を豊富に含んでいて、バランスがよい野菜といえる。
まず特筆すべきはビタミンB1、ビタミンB2が多量に含まれていることだ。
そら豆はエネルギー源となるタンパク質、糖質が豊富だが、同時に炭水化物のエネルギー代謝に必要なビタミンB1、脂質やタンパク質をエネルギーに変えるビタミンB2のほか、アミノ酸の一種であるアスパラギン酸も多く含まれており、疲労回復効果が非常に高いのだ。
特に疲労が溜まっているときには、にんにくと一緒に調理すると、にんにくの香り成分である硫化アリルがビタミンB1と結合し、アリチアミンに変化する。
そして互いの相乗効果でビタミンB1の吸収をさらに高めるのだ。
疲労回復効果がより高まり、食欲増進にもつながる。
ビタミンB1には、乳酸などの疲労物質が体にたまるのを防ぐ働きもある。
また、ビタミンB2には血管を若く健康に保ち、脂質の代謝を促す効果が高い。
ビタミンB2は余分なコレステロールが血管壁に付着するのを防ぐ効果もある。
さらにそら豆に含まれるレシチンという成分が悪玉コレステロールを下げるので動脈硬化も防いでくれるため、肝臓の機能保護に効果を発揮する。
生活習慣病の予防にも期待できるということだ。
そら豆はお酒のおつまみとして味のみならず栄養面でも最高の相棒なのである。
美肌効果・美髪効果
ビタミンB群の一種で赤血球の生成や細胞新生に重要な役割を担う葉酸、抗酸化作用のあるビタミンCも含まれている。
意識の高い女性はピンときたかもしれないが、実はそら豆には大きな美肌効果・美髪効果が期待できるのだ。
さらに女性が積極的に摂取するべき鉄分もあり、中年以降の女性にこそたくさん食べて欲しい野菜なのだ。
また、食物繊維が多く含まれているのも大きな特徴。
食物繊維の効果で便秘が解消することで肌荒れ改善・美肌効果も期待できる。
[ad#ad-1]
薄皮は絶対食べよう
薄皮とは、黒いそら豆を包む緑色の皮。
薄皮には食物繊維がたっぷりなので、捨てるのはもったいないのだ。
若い豆の薄皮は柔らかいが、成長が進んだそら豆は硬くなるので、食べる場合は煮るなどして柔らかくして、よく噛んで食べよう。
腸の働きが改善されて、便秘解消にもなる。
カロリーは意外と高めなので食べ過ぎに注意
バランスよく栄養がぎっちり詰まったそら豆。
ゆでたもので17~18粒を目安に食べるとそら豆の栄養を目いっぱい享受できる。
ゆでたそら豆100グラムのカロリーは、112キロカロリー。
100グラムで24粒、一粒で約4.7キロカロリーだ。
低カロリーというわけでは無いので、あまり食べすぎるのは控えよう。
旬の時期にそら豆をたくさん食べて、つやつやとキレイに、元気に毎日を過ごそう。
そら豆の基礎知識
そら豆の種類
そら豆は本来、豆単体ではなく、さやの中にある種子だ。

収穫時には巨大なさやえんどうのような形をしている。
食用そら豆には「早生種」「長さや種」「大粒種」の3種に分けられ、一般的に流通しているのは一寸系の大粒種だ。
豆は約一寸=3センチ程度。さやは15センチ前後だ。
1つのさやに平均して2~3粒入っている。
近年は「ファーベ」と呼ばれる生食できるイタリア産のそら豆が日本でも栽培されはじめている。
いいそら豆の選び方
さやの緑色が濃く、ハリとツヤがあり、中の豆の大きさが揃っているものを選ぶとよい。
さやの背筋の色が緑色でつやのあるものは鮮度が良い。
さやに茶色くなった部分があったり、背筋が黒褐色なものは収穫から時間が経っていて鮮度が落ちている。
そら豆の保存方法
そら豆は、豆類の中でも特に鮮度が落ちやすい。
おいしく食べられるのは3日といわれるほど鮮度が命なので買ってきたら早めに調理して食べよう。
すぐに調理ができない場合は、乾燥を防ぐためにポリ袋に入れて冷蔵庫に保存。3日以内に食べよう。
さらに保存したい場合は、冷凍することもできる。
生のまま冷凍すると、解凍したときに水分が流れ出して味や食感が変化してしまい、あまりおいしくなくなる。
さやから出して、薄皮をつけたまま硬めにゆでて密閉袋で保存する。
さやから取り出した状態で惣菜コーナーに売られているおつまみなどのそら豆は、店頭に並んでいるときにはすでに劣化が始まっているので、買ったらすぐ食べよう。
そら豆の重さの目安
そら豆を料理しようと思った際に、レシピがグラム表示だと何粒用意すればいいのかわからないので大体の重さを書いておく。
さや付きのそら豆10本で500グラム前後で、皮を除いた可食部は約25%のため、粒の部分は約125グラムほど。
1本平均3粒と考えると、ひと粒約4.2グラムだ。
そら豆の基本の調理方法
塩ゆで
ゆでる直前にさやから豆を取り出す。おはぐろ(口を開いたように見える箇所)部分に切り込みを入れると塩がよくなじんで風味がアップする。酒を入れると青臭さが和らぐのでおすすめ。余熱でも火が入るため硬めに茹でよう。
おはぐろ部分に包丁の根元で切込みを入れる
↓
水1リットルに対して塩大さじ1強を入れる。※塩は水の2%が目安
↓
酒大さじ1を入れる
↓
沸騰したら薄皮を付けたままのそら豆を入れる。
↓
2分半~3分ゆでる。小さいものや薄いものは火の通りが早いので調節しながら。
↓
茹で上がったら手早くざるにあげよう。
焼く
さやごとグリルで焼くと、さやのなかで蒸し焼き状態になりうま味が凝縮される。
熱を逃さないようにさやに切れ込みを入れずにそのまま焼く。
さやごと天板に乗せて、グリルで約7~9分焼く。魚焼きグリルでもOK。
↓
皮に焦げ目がついたら完成。
蒸す
さやごとアルミホイルで包んで、フライパンでお湯を加えながら火を入れると即席の蒸し焼き機になる。
さやにお湯が直接触れないようにするので水っぽくならずに、短時間でほくほく豆を作ることができる。
アルミホイルでさやを包む。
↓
フライパンに水を入れて沸騰させてそら豆を入れて蓋をして、蒸し焼きにする。お湯がなくなったら適宜補充すること。
↓
7~8分蒸して豆が柔らかくなったら完成。
揚げる
食物繊維がたっぷりの薄皮ごと素揚げすれば、超簡単栄養満点のおつまみが完成。
初夏の夕暮れにビールを飲みながら、この素揚げのそら豆が、もうたまらない。
さやから取り出した豆を160~170度の油に入れる
↓
豆が浮いてくるまで1~2分揚げる。
↓
油をきり、塩を振ってさあ召し上がれ。
揚げ料理の例
上手な食べ方
そら豆で捨ててしまうことの多い薄皮部分には、豆自体よりも食物繊維が多く含まれているため、食感が気にならない場合はそのまま調理してよくかんで食べたい。
そら豆にはグルタミン酸やアスパラギン酸といったうま味成分のアミノ酸が多く含まれているので豆自体の味をしっかり感じられる。
塩ゆでしただけでもうま味を感じることができ、おいしく食べられるのは天然のアミノ酸パワーなのだ。
栄養は抜群のうえに、油を使わないヘルシーな調理でもおいしく食べられる野菜なんてそうそう無い。
さらにさらに、カリウムを豊富に含んでいるので余分な塩分を排出してくれるうえ、マグネシウムには血圧を調整する効果があるので高血圧の人にもオススメ。むくみ解消効果もあるのだ。
世界のそら豆料理
そら豆は世界最古の農作物の一つと言われており、世界中で伝統的な料理が存在する。
そら豆の原産は北アフリカから西アジアと考えられており、新石器時代に栽培化された。
エジプトでは4千年前から栽培され、儀式に使われたという記録もあるのだ。
エジプトのピラミッドやトロイア遺跡からも化石化したそら豆が発見されている。
栄養価が高く、安価で、乾燥豆にすれば保存が効くことから広く世界中に広まった。
エジプトやスーダンなどでは朝食にはそら豆が必ず登場するほどだ。
日本へは奈良時代にインドの僧侶によって伝えられた。
世界各国で郷土料理として愛され続けているそら豆料理を挙げてみた。
中国
豆板醤(とうばんじゃん)
そら豆と唐辛子を主原料とする中国の発酵調味料。1700年台に四川省で最初に作られたのが始まり。唐辛子が多く含まれているためとても辛いが、加熱することで香りが立つ。麻婆豆腐をはじめ、四川料理には欠かせない調味料だ。
日本
お多福豆(おたふくまめ)
そら豆の大粒の品種を皮のまま鉄鍋などを使って甘く煮込み黒く仕上げたもの。
「阿多福」という字が当てられており、福を招く食べ物としておせち料理や祝い膳によく登場する。
お多福の面のようにふっくらしている。
レバノン
サラタ・フール・ビザイト・ザイトーン
そら豆のオリーブオイル仕立てのサラダ。柔らかく似たそら豆、オリーブオイルで軽く炒めた玉ねぎとにんにく、ざく切りコリアンダーをオリーブオイル、レモン汁であえて塩、こしょうで味付けして完成。冷やして食べる前菜だ。
スーダン
フール
そら豆を似た料理。スーダンやエジプトなどの伝統的かつ定番の朝食だ。
大量の塩と油を加えて、お好みでにんにく、チーズ、玉ねぎを入れたり、レモンを絞ったりしてカスタム。
毎日違う味に変化させてパンとともに食べる。
フールは有名なご飯です
スペイン
ミチロネス

乾燥そら豆と豚肉、チョリソを煮込んだスペイン南部のムルシア地方の郷土料理。
もどした乾燥そら豆と豚バラ肉、チョリソ、パプリカパウダー、オリーブオイルに鍋を入れて水をひたひたに注ぎ3~4時間煮込めば完成。
エジプト
ターメイヤ
柔らかくゆでたそら豆、パセリ、玉ねぎ、コリアンダーを香辛料で味付けし、ペースト状にして揚げたコロッケ。エジプトの定番豆料理。
中華諸国では「ファラフェル」として知られており、シリアなどではそら豆とひよこ豆の半々で作る。
イタリア
ファーベ・ペコリーノ
イタリアの生食できるファーベ種というそら豆に、薄くスライスしたペコリーノチーズを添えてオリーブオイル、こしょうを振ったおつまみ。ワインとファーベとペコリーノチーズを食べる習慣は、南イタリアの春の風物詩のひとつだ。
まとめ
いかがだっただろうか。
初夏を代表する野菜の一つ「そら豆」。
旬の時期にしか食べられないが、初夏はいちばんエネルギッシュに行動できる季節。
ぜひ天然のバランス栄養食「そら豆」を食べて、今年の夏は元気をチャージしよう。
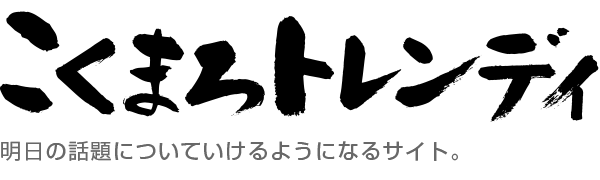

LEAVE A REPLY