
本当の賞味期限がわかる!
日本ではほとんどの賞味期限が実際の期限よりも2割以上短く設定されていることをご存知だろうか。
食品ロス問題に積極的に取り組む京都市の試算によると、1世帯4人の家庭の場合、年間6万円相当のまだ食べられる状態の食品が廃棄されているという。
賞味期限と消費期限の違い
賞味期限とは、「おいしく食べられる期限」のことだ。
この期限を過ぎたからといって、急に品質が下がって食べられなくなるわけではない。
これに対して、日持ちのしないお弁当屋お惣菜などに表示されている『消費期限』は食べても安全な期限を意味している。
こちらは表示の日にちを過ぎると急激に品質が悪くなるものなので、必ず期限内に食べなければならない食品だ。
賞味期限はどう決められているか
消費期限に比べて曖昧に思える賞味期限の設定。
賞味期限はどのように決められるのだろうか。
賞味期限は、製造日以降の菌の繁殖状況や、粘りや濁り具合を調べる実験、五感を使った評価などを総合的に判断し設定されている。
しかし、出荷後の食品は、その保存状態によって早く劣化する可能性がある。
たとえば、真夏にスーパーで買い物をしたあとに車のトランクに食品を入れて運ぶ間に品質が劣化し、早く悪くなってしまうケースがある。
そこで企業は安全のために、通常の保存状態で日持ちする日数に「安全係数」という数字をかけて算出した賞味期限を表示しているのだ。
その数値の設定は企業の判断に任されているが、消費者庁が推奨する目安は0.8以上、1未満。
安全係数が0.8の場合、賞味期限は2割ほど早まる計算になる。
たとえば18ヶ月日持ちするものでも、14ヶ月に設定され、賞味期限は4ヶ月前倒しになるのだ。
生鮮食品など品質の劣化が早いものは、万が一を考えて0.6などのもっと小さい係数が使われることもある。
安全係数はあくまでも目安であり、それを元にして決められた賞味期限も、ひとつの目安だ。
絶対的な期限ではない。
表示されている保管方法を守れば、賞味期限を過ぎた食品でもおいしく食べられる場合もある。
それでは、家庭でよく登場する食品を例に、本当の賞味期限を解説していこう。
本当の賞味期限表
卵
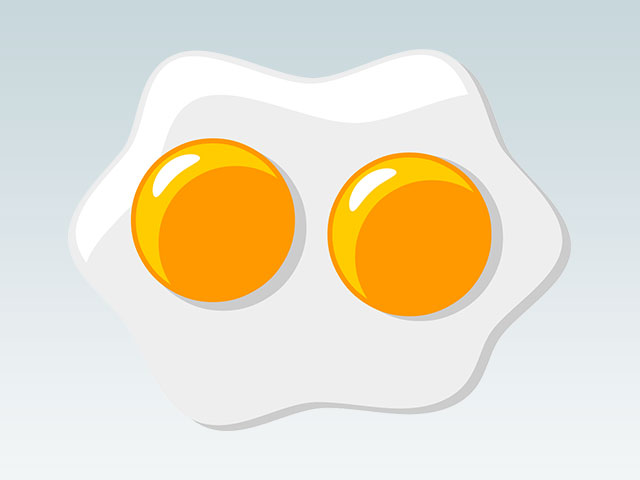
表示してある賞味期限+約1ヶ月半
日本での卵の賞味期限は、夏場に生で食べることを前提に計算されており。1年を通して採卵日から2週間と設定されている。
しかし本当は冬場なら気温10度以下で保存した場合採卵から57日間は生で食べられるのだ。
ただし、これは冷蔵販売されている卵の場合で、気温の高い場所で常温販売されている卵は菌の繁殖が早まる可能性があるので避けたほうがよい。
卵の賞味期限はあくまでも目安で、賞味期限を過ぎても加熱調理して食べる分には問題ない。
ただし、加熱調理後の卵はすぐに食べないといけない。
菌の増殖を防ぐリゾチームという酵素の働きが熱で失われてしまうためだ。
冬場なら気温10度以下で保存すれば採卵から57日間は生で食べることができることを覚えておこう。
納豆

表示してある賞味期限+2~3日
発酵食品である納豆の一般的な賞味期限は、1週間から10日間だ。
日が経つと熟成が進み、味に深みが出てくる。
発酵食品メーカーの社員の話では、賞味期限の切れたころが熟成していちばんおいしくなるのだという。
安全係数で短くなっていることを考えれば、賞味期限後、2~3日はおいしく食べられるといえるだろう。
同じ発酵食品であるヨーグルトやキムチも同じことだ。
数日中に食べきるなら、あえて賞味期限が迫って割引シールが貼られているものを狙うのも吉だ。
納豆は賞味期限が切れるころに熟成して美味しくなることは覚えておいて損はない。
なお、冷凍した場合は3ヶ月は保存することが可能。
カップ麺

表示してある賞味期限+約1ヶ月半
※袋麺は表示してある賞味期限+約2ヶ月半
インスタントラーメンはカップ麺なら表示してある賞味期限から約1ヶ月半、袋麺なら約2ヶ月は日持ちする。
しかし、最近はドラッグストアなどの店頭で直射日光を浴びる環境で販売されていることもあり、この商品は注意が必要。
長時間直射日光を浴びた食品は、未開封の状態でも酸化して品質が劣化してしまう。
そういう商品は買わないほうがいいだろう。
長時間直射日光で販売されているものは表示よりも早く悪くなることがある。
ドラッグストアなど、外にカップ麺を置いてる店では買わない方がいい。
レトルト食品

表示してある賞味期限+約3ヶ月
カレーやパスタソースなどのレトルト食品の賞味期限が製造日から1~3年。
もっとも短い1年のものだとしても賞味期限が切れてから約3ヶ月は持つ。
缶詰

表示してある賞味期限+約9ヶ月
缶詰の賞味期限は製造日から3年に設定。
安全係数によって2割短くなっていると考えれば、賞味期限が切れてからも約9ヶ月は日持ちするのだ。
塩分が高く味の濃いものや砂糖のシロップ漬けのものは賞味期限を12年過ぎても食べられるという実験結果も存在する。
さすが保存食の王様、缶詰だ。
味の薄い魚や野菜の水煮の缶詰は期限が切れてから約9ヶ月、味の濃いものはさらに長く持つ。
はちみつ

表示してある賞味期限+約6ヶ月
スーパーなどで販売されている密封パッケージのものに限る。
農家などで直接販売されているものは表示に従うこと。
梅干し

表示してある賞味期限+約2年
塩分の高い梅干しは日持ちする食品だ。
とくに塩だけで漬けられた『白干し梅干し』は賞味期限が切れても約2年は食べられる。
ただし減塩されているものはそこまで日持ちしないので賞味期限を守ること。
また、梅干しは高温多湿の場所だとカビが生える。
冷蔵庫で保存するようにしよう。
梅干しは製造年月日から1年の賞味期限が設定されているが、実際は3年持つ。
ただし減塩梅干しは表示に従うこと。
茶葉

表示してある賞味期限+1年半~2年半
市販の茶葉の賞味期限は、製造日から6ヶ月と設定されている。
しかし、実際は常温保存でも2~3年は持つ。
本当の賞味期限の決め方は自分の五感
基本的にほとんどの食品の賞味期限は短めに設定されていると考えてよいだろう。
しかし、たとえ同じ食品であっても出荷後の保管条件によって品質が保たれる期間も変わってくる。
まずは五感をフルに使って確かめよう。
水分が多いものはカビやすいので要注意。
実はスルメは意外と水分が高い。カビることがある。
また、健康な人には何も問題がなくてもお年寄りや子ども、病人が食べると体調を崩してしまう場合がある。
そもそも、賞味期限の表示が始まったのは1995年。
それまでは製造年月日のみの表示で、食べられるかどうかはそれぞれの感覚で判断していたのだ。
今は賞味期限表示に頼り切って思考が停止している状態とも言える。
捨てる前に五感を働かせて確認し、その感覚を子どもに伝えていくことが大切だ。
食品を無駄にしなければ、同時に家計の負担も減る。
昔のように五感を使って食品も家計も無駄を減らそう。
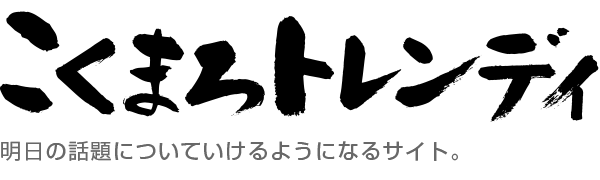

う~ん、なるほど。賞味期限と消費期限は違うのですね。勉強になりました。一番感心しましたのは「本当の賞味期限の決め方は自分の五感」!期限内であっても、その食品が美味か不味かを決めているのも自分の感性ですもんねえ。