
聞くだけで自律神経を整えるBGM
それ風邪じゃなくて自律神経の乱れかも!?
寝ても疲れが取れない…
便秘ぎみでいつもイライラ…
外出するのもおっくうで引きこもりがちになってしまった…
あなたの身に唐突に襲いかかる夏バテのようなダルさ、やる気が無くなるなどの謎の不調。
実はその原因は自律神経の乱れにあるかもしれません。
今回は、現代人にとって切っても切れない「自律神経」について解説します。
そもそも自律神経って何?

自律神経とは、自分の意志とは無関係に働いてくれる神経系のこと。
寝ているときにも心臓が動いてくれること。何も考えなくても息を吸ったり吐いたりできること。暑いと汗をかいて、寒いと身体をガタガタと震えさせて体温をキープしようとすること。
これらはすべて自律神経のおかげです。
自律神経は血管や代謝、呼吸、体温調節などをコントロールしています。
いわば命の司令塔。
自律神経には身体を緊張させる“交感神経”と身体をゆるめる“副交感神経”の2つがあります。
健康な人はこの交感神経と副交感神経のバランスが均衡を保っている状態です。
交感神経と副交感神経のバランスが崩れてしまうと、食欲や睡眠、血液、排便などに何らかの悪影響が発生します。
症状が軽いと何もせずに放置しがちですが、現代人こそ自律神経に注目してケアすることが大事です。
日常のちょっとしたことに意識を向けるだけでだいぶ改善できるので、ぜひ実践してみましょう。
交感神経と副交感神経って何?
自律神経は交感神経と副交感神経の2つに分かれており、2つの自律神経のバランスが崩れたときに、体に様々な不調が発生します。
交感神経→アクセル
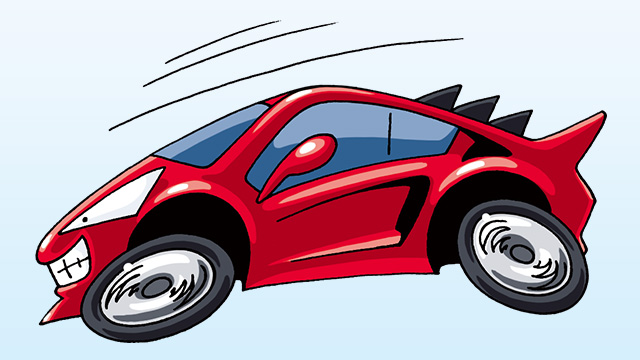
交感神経とは、緊張・興奮させるなど「アクセル」のような働きをつかさどる神経。
“スポーツをする”“家事・仕事をする”など、体が活動しているときは「交感神経」が優位になります。
ストレスを控えている、勤務時間が長いなどの緊張状態が続くと、交感神経の働きが過剰になり、自律神経の乱れにつながります。
副交感神経→ブレーキ
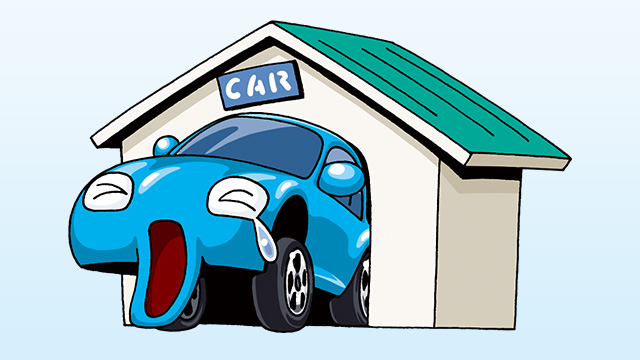
副交感神経とは、身体をゆるめて落ち着かせる「ブレーキ」のような働きを司っている神経。
“リラックス”“睡眠中”など、身体の疲れを回復しているときは“副交感神経”が優位な状態です。
副交感神経があまり働かないと、疲れが取れない、身体がダルくて重いなどの状態を引き起こしてしまうことになります。
ストレスフルで不規則な生活を送る現代人は、交感神経が活発になり、身体の修復や新陳代謝をしてくれる副交感神経の働きが鈍くなっています。
すると血管やリンパの動きが鈍くなるため、冷え・便秘・頭痛・肩こり・生理不順・生活習慣病など身体の不調となって表れるのです。
さらに、交感神経が活発な状態が続くと、血流が悪くなり体内に十分な栄養が行き届かなくなるため、免疫機能が下がり、すぐ風邪をひく身体になってしまいます。
[ad#ad-1]
自律神経を整える15の方法
手間を掛けずに自律神経のバランスがよくなるメソッドをご紹介します。
“自律神経のバランスをよくする”というとなんだが大変そうな気がしますが、実はとても簡単。
一番大切なことは、“しっかり睡眠を取って適正な時間に起床して活動する”だけ。
自然の流れに逆らわない生活をしていれば、自律神経は自然に整っていきます。
“質のいい睡眠づくり”“身体が回復しやすい生活”この2つのポイントを意識することが非常に大事です。
遮光カーテンをつけずに朝日で目覚める

寝室のカーテンは適度に日差しを感じるものにして、朝日を浴びる習慣を作りましょう。
朝起きたときに朝日を浴びると、体内時計がリセットされます。
交感神経が優位になり、脳も起きたことを認識するため、体をしっかりとオフからオンの状態にすることができます。
脳内物質“セロトニン”もたっぷりと分泌されるのため、さわやかな気分とやる気をもたらしてくれるのも大きなポイントです。
朝食をしっかりとって副交感神経を上げる

朝目覚めたときは交感神経が優位になっている状態です。
交感神経が優位な状態が続くと、体にストレスを与えてしまいますが、朝食を摂ることでいったん副交感神経を優位にすることができます。
まず、食前に1杯の水を飲んで胃や腸の働きを促します。
そしてよく噛んでゆっくり食べることで、副交感神経を上げることができます。
1つの大きなストレスをたくさんの小さなストレスに変換する
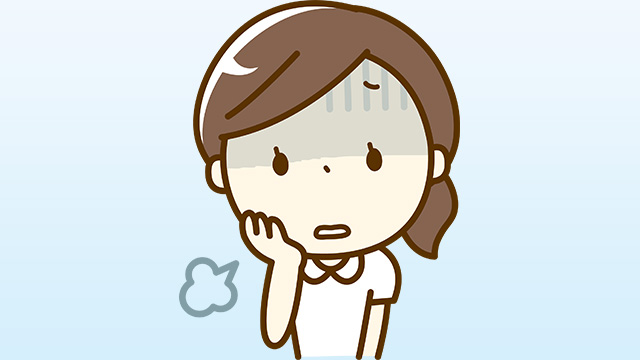
ストレスは交感神経を活発にするため、自律神経を乱す大きな原因ですが、誰しもストレスをゼロにすることはできません。
そこで大きなストレスを分割して、“たいしたことない”と自分に思い込ませるという方法があります。
例えば「夫が嫌い」という大きなストレスがあった場合、夫の何が不満なのかを細かく分割していきます。
『「ありがとう」を言ってくれない』、『夜ご飯を準備したのに連絡が無い』など、細かいストレスに分割することで、逆にそれ以外の部分を見直したり認めることで、大きなストレスを小さくしていくことができます。
おしゃべりは最高のリラクゼーション

女性はコミュニケーション脳が発達しており、おしゃべりすることで自然とストレス解消ができるようになっています。
人は楽しいことをしていると副交感神経が優位になり、気持ちも身体も修復する機能が働きます。
今度友人とこんなお店でランチしようかなと妄想するだけでも効果があるのです。
深呼吸は副交感神経を一瞬で活性化できる!

口だけでハッハッと息する浅い呼吸では身体の緊張はほぐれません。
イライラしていたり体が重いと感じたら、深呼吸して副交感神経を活性化して身体をゆるめるクセをつけましょう。
まず息を吐ききります。すると自然にたっぷりの空気を吸い込めます。
外出時はサングラスを持ち歩く
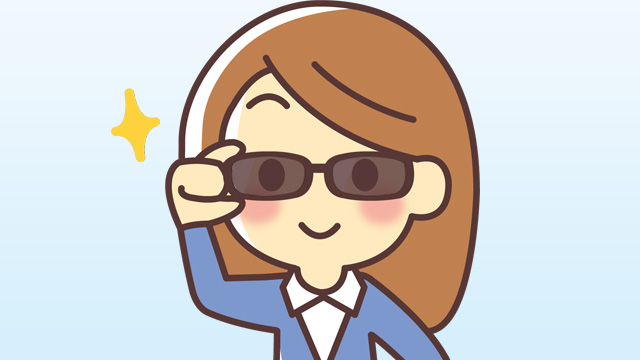
紫外線を浴びすぎると体内で活性酸素が生じて疲れが溜まって自律神経を乱す原因になります。
長時間外に座っていると、身体が疲れたように感じたらこの現象です。
外出時はスキンケアも兼ねて日焼け止めを塗るのはもちろん、さらにサングラスをかけて目から入る紫外線もカットするとよいでしょう。
食物繊維を意識的にたっぷりとる

“便秘=自律神経の乱れ”といえるほど、自律神経と腸は密接な関係にあります。
便秘解消には食物繊維が必要不可欠。
納豆のトッピングに食物繊維が豊富な海藻類をのせる、白米に雑穀米を加えて炊くなど、いつもの食事にちょいプラスする意識を持つとよいでしょう。
鶏肉料理を食べて脳の神経伝達物質を刺激

副交感神経の働きだけでは身体を十分に回復できません。
そこで週一回以上、疲労回復効果のあるイミダペプチドを多く含む鶏肉(特に胸肉)を食べると、体のメンテナンスを促進してくれます。
間接照明で身体を夜モードに演出する
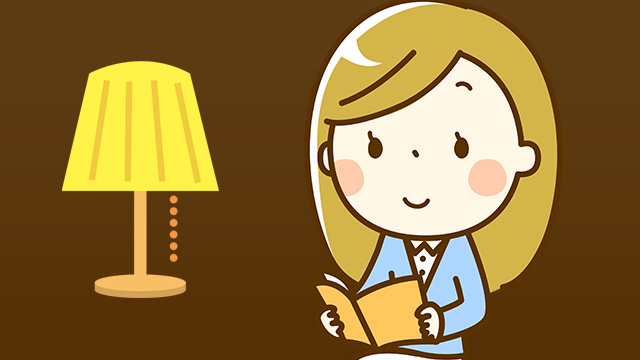
朝は自然の日差しで交感神経を高めますが、夜は身体に「そろそろ休みますよ」と信号を送って副交感神経を活性化させることが必要です。
寝る前に過ごす部屋の照明は強い光のものは避け、優しい光の白熱灯タイプの間接照明に切り替えるとよいでしょう。
昼間はアクセル、夜はブレーキという流れを身体に覚えさせるとよい。
葉のゆらめきなど、自然の音に耳を傾ける

小鳥のさえずり、木々の揺れる音、風が吹く音などなど…。
自然の音には“ゆらぎ”という現象があり、耳をすませるだけで疲労回復効果があります。
近くに自然がなければ、街の音に耳を傾けるだけでもOK。
副交感神経が活性化され、リラクゼーション効果が期待できます。
【自律神経を整える音楽】自然音 川のせせらぎ【癒し系】
湯の温度は39〜40度で入浴は“ぬるめ&ゆっくり”

お風呂に入ってリラックスモードになろうとしても、肌にジリジリとくるような高温のお湯では、逆に身体が活動モードになってしまいます。
お湯の温度は、じんわりと温かさを感じる40度前後がよいです。
浴室の照明を落とし、水などを飲みながら湯船に浸かり、10〜15分ほど入浴するのがベスト!
寝る前1時間はスマホもテレビも見ないこと

スマホやテレビなどブルーライト越しの情報は、脳が覚醒して交感神経が活性化します。
そのまま眠りにつくと、身体は寝ていても脳は活動しているというアベコベの状態になってしまうため、自律神経が大きく乱れてしまいます。
睡眠時間は十分でも体のダルさは取れないという、非常に不快な状態になってしまいます。
寝る1時間前を目安にスマホ&テレビはオフにしましょう。
下半身の血流をよくしてぐっすり睡眠
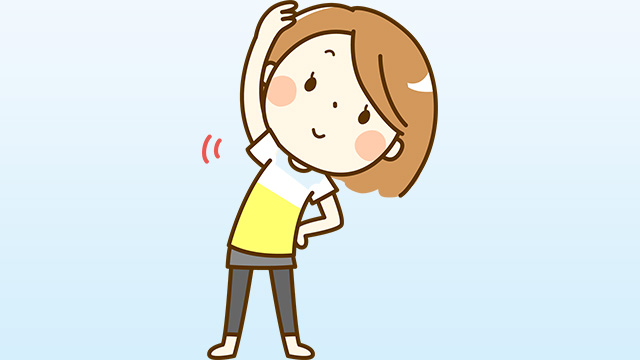
入浴後にあお向けに寝てひざを立てて、左右にゆっくりゆらして股関節をほぐします。
こうすることで、下半身の血流が良くなり、冷えの改善にもつながります。
さらに腰回りのリンパがゆるめられるので寝つきも良くなります。
もちろんリラックス効果も大きく、副交感神経も活性化されます。
入浴中に下半身をソフトにもみほぐすのもおすすめです。
布団から片方の手のひらを出して就寝する
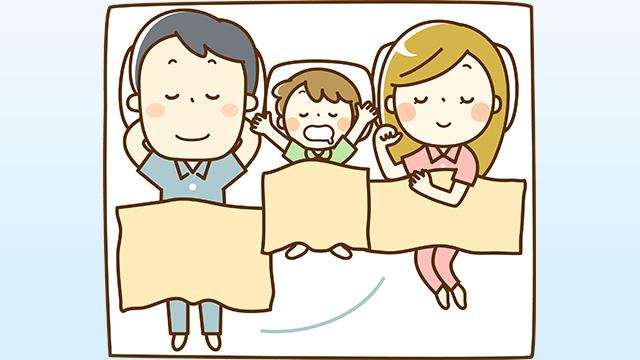
手のひらが温まるとだんだん体温が高くなり、交感神経が優位になっていきます。
結果眠りが浅くなり、自律神経のバランスが崩れます。
布団からどちらかの手のひらを出して、足元はしっかり温めるとよいでしょう。
少し固めのマットレスで寝返りをしやすい状態に
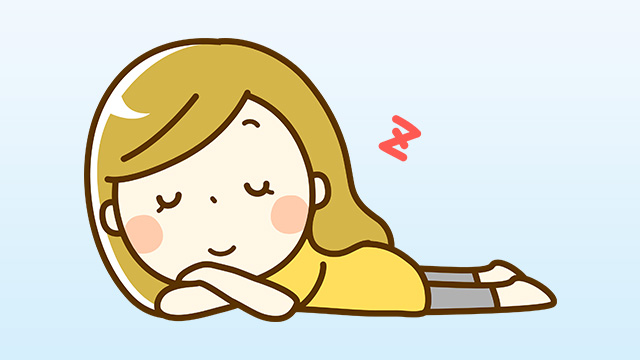
就寝中に気をつけなければならないのは寝返りのしやすさ。
身体が硬く縮こまった状態だと、寝ているのに緊張状態となって交感神経が高ぶってしまうため、自律神経のバランスが崩れます。
少しだけ固めの枕とマットレスを使い、ゆったりとしたスペースを確保するとよいでしょう。
寝返りを打ちやすい環境が深い睡眠につながります。
自律神経に効くおうちマッサージ
自律神経が整う3つのツボをご紹介します。
ポイントはツボをイタ気持ちいい程度に押すこと。
どのツボも全身の血液を促すので押すと身体がポカポカしてくるはずです。
押し方は強すぎても弱すぎてもダメです。
自分の中の“イタ気持ちいい”具合を見つけるとよいでしょう。
風呂上がりにやるとさらに血の巡りがよくなって効果がアップしますよ。
【ツボ1】合谷(ごうこく)を押す

手の人差し指と親指の骨が交わるあたりのくぼみが合谷。
ここをジーンとイタ気持ちいい程度に数回押しましょう。
胃腸を活発にする効果があり、便秘解消にもなる。
【ツボ2】爪の生え際をもむ

手の爪の生え際をゆっくりやや強めに10秒押します。
すべての指に行うとよいでしょう。
冷えの改善にも効くので末端の冷えで悩む人はぜひ試してもらいたいテクニック。足の爪で行っても同様の効果があります。
【ツボ3】“第2の心臓”ふくらはぎをもむ

“第2の心臓”ともいわれるふくらはぎを、下から上へなで上げながらもんでいきます。
くるぶしの下とひざの裏は特にもみほぐします。リンパの詰まりを解消できます。
[ad#ad-1]
まとめ
いかがだったでしょうか。
昔の人は季節の変化に合わせて自律神経の調整が自然とうまくできていました。
現代人はエアコンや照明機器の発達により、気温や太陽の働きに応じて自律神経を調整する機能が減退しているといわれています。
さらにスマホやネットを寝る直前まで見続けるなど、24時間情報という刺激を受け続けていると、脳が休まることはないのです。
オンとオフの切り替えがない生活が自律神経のバランスを崩してしまっているのです。
自律神経は環境に応じて揺れ動きます。
重要なのは“適正なところに戻す力”を養うこと。
日々の習慣を少し変えれば自律神経の揺れを調整できるのです。
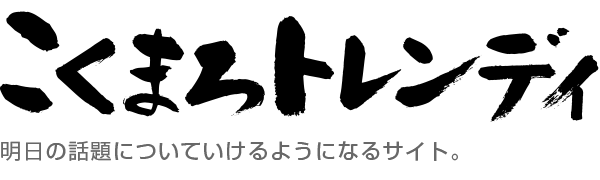

LEAVE A REPLY